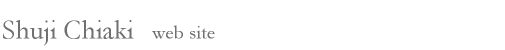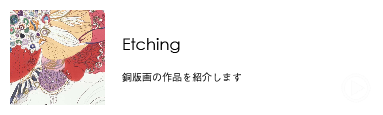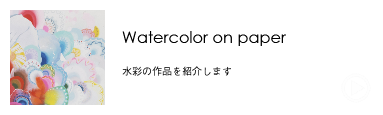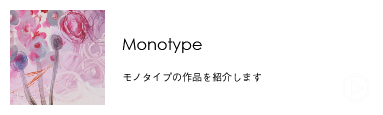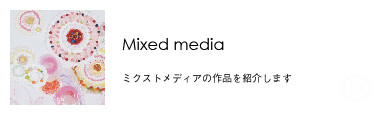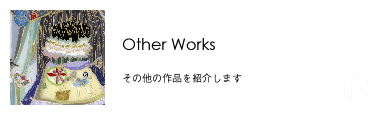集治千晶の表現
限りなく透明に近い感性の世界
集治千晶(シュウジチアキ)は1973年京都生まれの日本の女性作家である。韓国の年で37才になるが、およそ30回近くの個展を開くほど精力的な活動を広げている。大学と大学院で版画を専攻し、絵画は勿論、版画家としてもよく知られている。賞運もあり、ポーランドのクラコ国際版画トリエンナーレをはじめあらゆる国際展で多様な賞を受賞している。
しかし韓国で彼女の作品が紹介されたのは空間国際版画ビエンナーレ(2002)とSIPA写真アートフェア(2005)を除いてほとんどその機会がなく、今回開催される珍画廊招待展が彼女の作品を本格的に味わうことのできる最大の展示となるだろう。
 2008年、京都のアトリエにて
2008年、京都のアトリエにて
集治千晶の作品の世界は、華やかな色を土台とした多様な線のバリエーションが特徴である。彼女の作品は版画と水彩画に大別されるが、それらは内容によって区分されるのではなく媒体により分類される。したがって同じ内容でもその場合によって、水彩画でも版画でも制作できるということなのである。これは彼女にとって版画の比重が非常に大きいという事実を物語っている。
集治千晶の作品は華やかで繊細なのが特徴だ。色に対する日本的感覚が自然に現れたのが彼女の作品といえる。色のにじみ効果(渲染)に基盤を置く設彩法が中心となっており、その土台の上に色と線が意識の自由な連想によってあたかも超現実主義者などが好んで使った自動技術法(automatism)のように絡まり、画面を美しく彩っている。花、宇宙、スパークリング、空などが主な素材として登場する。よって彼女の作品を見ていると、あたかも作家の意識が遊泳する場面を見るようである。
一つの花びらがもう一つの花びらを産み、それは再び他の花びらを産むことになるのだが、結局は見事な花一輪が誕生をすることになるのである。しかしその花は自然の花ではなく花を連想させるイメージであるすぎず、描写された完全な花ではない。集治千晶の絵に登場する花は、作家の意識の中で解体されて再び組合わされる、そして数知れず分離する過程を経た‘心象的イメージ’としての花なのである。
集治千晶の絵に頻繁に現れる要素は線だ。彼女の作品は、自由な連想による線描が華やかな色彩と出会い美的効果を極大化した地点に立っている。純度の高い暖色と寒色の絶妙の出会いということができる。
色の経営自体だけを見ればほとんど抽象に近い様態を帯びているが、そこに線描が付け加えられることにより多様な意味と象徴が誕生している。細く鋭い実線と点線の使用は形態を産む。
手、花、子房、幹、レース等等、しかしそれらは具体的というよりはやはり暗示的であり、何かを連想させるだけである。
生命を誕生させる子宮のようでもあり、かと思えば花の奥深い内部のようでもある。結果的にはそのどれだとはっきり結論づけられない、あいまいな第3の形態を産んでいるのである。
近くは花から遠く宇宙に至るまで、自然を探索する集治千晶の作品世界は、あたかも風に乗って飛び回る胞子のように自由な連想による線が色を
‘閉じ込めることによって’誕生する。
その絵から線をなくしたら、今にも透明な色の水があふれ出てくるかのようだ。
ともするとややエロチックともいえるこの透明な感覚の世界が、まさに集治千晶が追求する芸術の本質ではないかと考える。
尹晋燮 (美術評論家/湖南(ホナム)大教授)
2009年3月 集治千晶・ソウル珍画廊の個展より